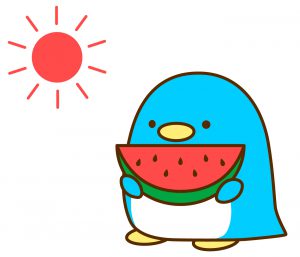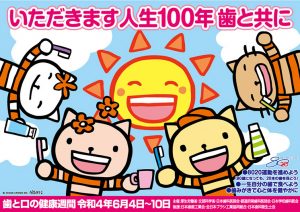- インプラント (4)
- こども歯科 (8)
- シニア歯科 (11)
- セミナー情報 (3)
- デンタルグッズ (6)
- ラグビーのお話 (6)
- 予防歯科 (5)
- 出張国内 (2)
- 出張外国 (2)
- 医院情報 (11)
- 医院通信 (4)
- 妊婦さんの歯科治療 (2)
- 未分類 (28)
- 歯周病 (9)
- 歯科情報 (28)
- 診療のお知らせ (21)
- 院長の写真 (6)
インフルエンザと歯磨きの関係?
お口の中を不潔な状態にしておくと細菌が増殖し、インフルエンザに罹り易いというデータがあります。
実際に、介護施設や小学校などで歯磨き指導を徹底したところ、インフルエンザ罹患率が低下したという報告もあります。
お口の中の細菌とインフルエンザの関係は深く関りがありますので、正しい歯磨きを身に付ける事が感染症予防として重要です。
毎日の歯磨きをしっかりおこない、歯科医院での歯周病や虫歯の治療、歯のクリーニング(PMTC)などをおこなうことで口の中の細菌を減らすと、
プロテアーゼやノイラミニダーゼの量が減り、インフルエンザの発症も抑えられるとされています。
歯磨きはただすれば良いという事では、むし歯や歯周病の予防が出来ませんので
歯並びによって正しく磨けるように歯科医院の歯磨き指導をお受け下さいね(^^)
歯周病は遺伝する? 2023.01.17更新
歯周病は遺伝する?
歯周病は遺伝するのでしょうか?
歯周病そのものが遺伝するということはありません。しかしながら、非常に少ない例ですが、遺伝性要因があるとされる歯肉の増殖特殊な歯周病があります。
また、近年、遺伝子診断により、本当に遺伝的になりやすい人、なりにくい人がいるかどうか科学的に解明されつつあります。
歯周病にかかりやすい、かかりにくいはある?
大きく分けて口の中の状態と全身状態によります。
お口の状態ですと歯並びや歯周病菌の種類や粘膜の形が影響しますし、身体全身の場合は生活習慣(喫煙など)やそれに関する病気(糖尿病など)、遺伝的影響など、色々な要素が関わって歯周病にかかりやすくなるのです。
また、遺伝子診断、免疫応答・炎症反応の検査により歯周病にかかりやすい患者さんがいると報告されています。
特に通常は40歳前後に症状があらわれる歯周病が10歳代後半からあらわれる早期発症型と呼ばれる歯周病がこれにあたります。
歯周病は早期発見に勝るものはありません。
症状が何もなくても定期検診をしっかりと受けましょう★
嚙み合わせが悪いとどうなる 2022.12.12更新
こんにちは、下地歯科です。
皆さんは「嚙み合わせ」を気にされたことはありますか?
いつも左右どちらかの歯で噛んでいる、いつも同じ方の足を組んでいる、このような癖はありますか?
何気ない仕草ですが実はこれ、嚙み合わせを悪くする習慣なんです!
良い嚙み合わせと悪い嚙み合わせ
嚙み合わせが良い状態とは?
・歯列が綺麗な半円形になっている
・上下の歯の山がしっかりと噛みあう
・噛むときに多くの歯にバランスよく力がかかる
悪い嚙み合わせ
・上の前歯と下の前歯の真ん中がずれている
・下の前歯が半分以上、上の前歯に隠れている
・上下の歯の接触部位が少ない
・上の前歯と下の前歯のすき間が5ミリ以上ある
嚙み合わせが悪いとどうなるの?
・むし歯になりやすい
・知覚過敏になりやすい
・歯周病の悪化リスク
・咀嚼機能が定期する
放置するとゆがみの原因にもなります。永久歯が抜けたけど放置した、などは非常に危険ですので、必ず受診するようにして下さい。
知覚過敏 2022.11.15更新
こんにちは、下地歯科です。
歯がしみる!と感じた事がある方は多いかと思います。
知覚過敏は、歯肉が下がり軟らかい象牙質が露出して起こります。
象牙質には神経に通じる細かい管が無数にあり刺激が直接神経に届いてしまうのです。
知覚過敏はこんな時に感じやすい?
・冷たい、または甘い物を飲食した
・歯ブラシの毛先が触れた
・冷たい風にあたった
知覚過敏の治療方法
・再石灰化を促す
唾液により再石灰化で象牙質を修復します。
・専用の歯磨き粉を使う
歯の神経の鎮静作用があり徐々に治まります
・クリニックで治療
刺激を受けにくくする薬剤を塗布し、プラスチック材などでコーディングします。
痛みがひどく日常生活に支障をきたす場合は、歯の神経をとる事もあります。
知っておきたい関連疾患!
〇根面う蝕
軟らかい象牙質が露出したままだと歯根根面のむし歯「根面う蝕」を起こしやすくなります。怖いのは歯の神経に近いので上昇になりやすいです。歯肉が下がってきたら要注意です。
歯がしみる、と感じた方は早めの受診をお勧めします。
【歯磨き】 2022.10.19更新
歯ブラシを力いっぱい歯に当ててしまうと、毛先が広がってしまいプラーク(歯垢)がしっかり落とせません。
力を入れ過ぎる「オーバーブラッシング」と言います。
磨くときは広い範囲に大きく動かすのではなく、狭い範囲を小刻みに動かしたほうが細かいところまでプラークを落とせます。
ライオンが20代から60代の男女約1000人に、
「歯をやさしくみがく」か「強くみがく」か、大別すると自分はどちらに入るかをたずねたところ、「やさしくみがく」と答えた人が約4割、「強くみがく」と答えた人が約6割でした。
歯磨き粉の量は多いほうが良い?
テレビCMなどでつけている歯磨き粉の量を真似してしまうと実は良くありません。
口の中が実際よりもきれいになったように錯覚してしまうからです
歯磨き粉をたくさん付けて歯を磨くと泡立ちすぎてしまい、きちんと磨ける前に磨いた気になってしまいます。
舌や歯にミントの香りや感触が残っていても、歯垢が残っている可能性があります。
ですので歯みがき粉を選ぶさいは、低発泡のものにしましょう。
歯ブラシは濡らすべき?
答えはNOです。
これも濡らしてしまうと泡立ちが良くなってしまうからです。
歯磨きの目的は、歯と歯の間に入り込んだ食べかすを取り除いたり、歯の表面についた汚れやむし歯や歯周病の原因菌が住み着いているプラークを取り除くことです。
しっかりと磨いているのにむし歯になる、という方は磨き方や歯磨き粉の量に問題がある可能性があります。
定期検診などで正しい歯の磨き方、歯磨き粉の使い方を身に付けて下さい。
歯科医院で販売している歯ブラシや歯磨き粉は使いやすいものが多く歯科医師、歯科衛生士のお勧めを取りあつかっています。
今まではドラッグストアなどで購入していたという方は一度歯科医院でお勧めを聞いてみるのも良いと思います。
スケジュールです★ 2022.09.13更新
こんにちは、下地歯科です。
【9月のお知らせ】
9月20日(火)16時半まで
21日(水)9時半11時半まで
22日(木)16時半まで
【10月のお知らせ】
10月5日(水)、9時半~16時半
12日(水)9時半~17時半
13日(木)9時半~16時半
14日(金)9時半~15時半
18日(火)19日(水)9時半~16時半
25日26日9時半~16時半
27日(木)9時半11時半
28日(金)9時半~16時
29日(土)休診
よろしくお願いいたします。
抜歯 2022.08.10更新
こんにちは、下地歯科です。
歯科治療で歯を抜く時のお話を更新します。
歯を抜くとき
その①むし歯の進行状態
むし歯を放置して進行すると細菌に感染して、歯を支えている骨が溶けたり、歯ぐきが激しく痛むといったさまざまなトラブルの原因となります。
また、歯の根の先端が細菌に感染して膿がたまっている場合も、骨などへの感染を防ぐため歯を抜くことがあります。
その②歯周病
歯周病は細菌によって歯を支える骨が溶けてしまう病気です。
むし歯のように、初期の段階で症状を感じる事が少なく、「歯周病で歯を抜かなくても…」と思われる方は少なくありませんが、
歯がぐらぐらするほど歯周病が進行=重度の状態、になり、その歯をそのまま残しておくと、周辺の健康な歯までもが歯周病に侵されてしまう恐れがあるのです。
そのため、歯周病でぐらぐらになった歯は将来のお口の健康のために抜歯の選択が候補として挙げられます。
その③歯根破折
歯根破折は、歯が根元部分から、中から割れてしまう歯の病状を指します。
歯根というのは歯の下部、歯槽骨の中を指しますが、この部分から歯が割れていき、最終的には歯の表面部分も割れてしまうことのある病状です。
このような場合は、周囲への影響を考え抜歯を選択することがあります。
いかがでしょうか・・。
自分の歯を抜く選択をしなくてはならない場合、とても辛いですよね・・。
こうなる前に早期発見、早期治療が大切になります。
大切な自分の歯と歯茎を守るためにも、検診は重要なのです。
それではまた更新します。
夏季休診のお知らせです。 2022.07.13更新
こんにちは、下地歯科です。
8月14,15,16日は休診します。
宜しくお願い致します。
6月4~10日は 歯の衛生週間 2022.06.04更新
6月4~10日は 歯の衛生週間
6月4日は6(む)と4(し)の語呂合わせで、「むし歯予防の日」です。
また、6月4~10日までの1週間は、厚生労働省・文部科学省・日本歯科協会などが「歯の衛生週間」を実施しています。
日本人男性の平均寿命は78歳、女性は85歳と、世界一の長寿大国です。
しかし、残念ながら、歯の寿命は50~60歳代で、高齢になるに従って、歯を失う人が多いのが現状です。
日頃から歯磨きなどの口腔ケアをしっかり行っていれば、歯の寿命をもっと延ばすことができます。
最近では、80歳まで20本の自分の歯を持とうという「8020運動」も提唱されています。
「歯の衛生週間」をきっかけに、歯を長生きさせるための口腔ケアを実践する習慣を身につけましょう。
抜けた歯を放置してませんか? 2022.05.20更新
こんにちは、下地歯科です。
何らかの原因で抜けてしまった歯をそのまま放置してはいませんか?
特に問題がないからといって、そのままにしている方は少なくありません。
1本歯がないくらいでは、食べるときにそれほど不自由はしないですよね。
しかし、歯が無い状態は、実は皆さんが想像している以上に大きな悪影響を及ぼします。
お口の中は家の柱と同じで、歯が1本でも抜けたままにしていると、歯全体が崩壊していきます。家の柱も1本ないと崩壊してしまいます。
まず、奥歯が無くなると確実に「噛めなく」なります。
奥歯は食べ物を消化しやすくし、歯列全体のバランスをとっています。奥歯が1本でもなくなると、慢性的な肩こりや頭痛の原因にもなってしまいます。
奥歯は、運ばれてきた食べ物を臼のように細かくすりつぶし、消化しやすくする働きがあります。
前から6・7番目の奥歯(大臼歯)を1本失っただけで、すりつぶす力が30%も落ちると言われています。
食物をうまく咀嚼できずに飲み込んでしまうため、胃や腸に負担がかかるようになります。喉を傷つけることにもなりますし、消化不良で栄養も十分に取れなくなってしまうのです。
さらに、唾液の自浄作用の働きも弱くなる為、虫歯や口臭の危険も高まります。
重要なことは見た目が悪かったり噛みにくいなど、抜いたところだけの問題にとどまらず、反対の歯や両隣の歯などほかの歯にもトラブルが起こしたりもします。
歯が1本だけなくても生活に支障が無い、と思われているかもしれませんが、それは大きな間違いなのです。
1本でも失うと、確実に将来的にお口全体が崩壊していきますので抜けた歯をそのままにしておくのはよくありません。
必ず受診するようにして下さいね。